![]()

碓井秀典(東京都港区在住 原水出身)
ステラーコミュニケーション株式会社
976号 2020年1月19日
(1)替り目
明けましておめでとうございます。今号からワンネスにご縁を頂き連載を始めることになりました碓井秀典と申します。菊陽町原水出身で、現在は東京でデザインの仕事をしています。落語が好きなので落語の話をさせていただきたいと思います。
私が落語を聞き始めたのは、2011年の2月で一人で仕事を始めてから半年経った頃でした。仕事がうまくいくのか不安で、気持ちを切り替えたいと神楽坂毘沙門天で行われる落語会に行ってみたのが最初です。ですから8年半くらいで、実はあまりたいしことはないのです。ただ、その世界のことを知り始め、ちょっと分かってくると「誰かに伝えたい、話をしたい」という気持ちが募り、落語会のはねたあとで、友人たちと反省会と称して飲んで話しているだけでは飽き足りず、今回の連載に至った次第です。どうぞよろしくお願いします。
「独断!」とタイトルにありますように、私の好き嫌いに基づく内容になっています。お読みになった方には、ご不快な気持ちを抱かせてしまうかもしれません。そうなりましたら、大変申し訳ありません。先にお詫びをしておきます。
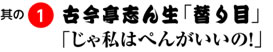
第1回目は古今亭志ん生(五代目)です(多分、この後も何回も出てくるかと思います)。音源が残っている人というとやっぱり戦後になりますから、それ以降で言うとやはり志ん生が第一人者でしょう。昭和の大名人と言われていて、私などが言う必要もないのですが、破天荒・天真爛漫と評され、うまさはもちろん、話し方のスタイルや格調、言葉遣いの丁寧さ、滑稽話・人情話、どれをとっても大名人と呼ぶのにふさわしい噺家です。
噺は何を選ぶか! ここが問題です。「火炎太鼓」「富久」「強情灸」「文七元結」「淀五郎」「風呂敷」「猫の皿」……。私が挙げたいのは「替り目」です。この噺は「酔っ払い噺(こう言う分類があるかは知りません)」の一つで、志ん生は前段と後段を思いっきりカットして夫婦の対話のところだけで演じています。「酔っ払い噺」は、下手が演ると、酔態を強調するあまり、下品な感じであまり好きではありません(自分のことを棚に…)。
今はこの志ん生の型が主流だと思いますが、前後をカットしたことが良かったのだと思います。志ん生の魅力の点を先ほど挙げましたが、「可愛らしさ」というのもあり、これがよく現れている噺かとも思います。志ん生の実生活から生まれたと言われていて、その通りなのだと思いますが、それを知らなくても充分に楽しめます。
980号 2020年2月23日
(2)時うどん
連載第2回目ということで、迷った揚げ句「時うどん」にしました。元々は上方の噺で東京の方では「時そば」になります。食文化の違いでしょうか、江戸っ子はうどんが嫌いだったようです。私も初めて東京に出てうどんを頼んだ時、出てきた黒い汁に入ったものを見て「ぼ、ぼくが頼んだのは、う、うどんですっ!」と思わず言いそうになりました。それを思えば嫌いなのも、もっともだ思います(今は慣れてしまって食べてます)。
東京版では、傍で見ていた男が真似をするのに対し、上方では兄貴分と弟分の二人が登場し、感心した弟分が翌日真似をしてしくじってしまうという型になっています(東京でも春風亭昇太がこの型でやっています)。「付け焼き刃モノ」(私の分類)の一つです。「今、何時だい?」のセリフがすっかりおなじみで、オチも変えようがないので、噺家たちは2軒のうどん屋の、味やしつらいを真逆にし、そのギャップで笑いを取るという工夫をしています。
この噺で重要なのは、現代と江戸時代の時法が違うということで、長くなりますが、日没(暮六つ)から夜明け(明け六つ)までを6等分し一刻(とき)とし、六つから五つ、四つと数え、次は(なんと!)九つ、八つ、七つ、そして夜明け(明け六つ)と続いていく、という時刻の数え方をしていたんですねぇ!(だから、夏と冬、昼と夜の単位時間の長さが違っていたんですねぇ!「不定時法」というらしいです)。真似した男のしくじった原因がここにあったんですね。ちょっと早く出すぎちゃったんですねぇ!
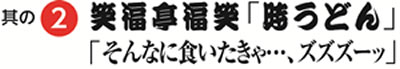
さて、普通の「時そば」ならご覧になる機会は多いかと思いまして、ここでは上方の笑福亭福笑(上から読んでも下から読んでも…)のものをご紹介します。六代目笑福亭松鶴の三番弟子です。新作・古典両方やりますが、古典は工夫が盛り沢山で「改作」にかなり近いものになっています。何の工夫もなければ落語は廃れてしまいます。新作は好き嫌いの別れるところだと思いますが、私は暴走系・スタンピード系と呼んでいます(上方には多いんだ!)。私は大好きです。古典では「桃太郎」「千早ふる」、新作では「憧れの甲子園」「今日の料理」(大丈夫なのかぁ?)などで、別の機会に是非取り上げたいと思っています。
時法のことも、他の噺家も説明している人はいますが、福笑はまくらできっちり押さえています。
983号 2020年3月29日
(3)壺算(つぼざん)
今回は「壺算(つぼざん)」。冷静に考えれば何でもないことでも、パニックに陥ってしまうと人はほんとにパニクってしまうというお話。「チョロマカシモノ(詐欺話)」の一つ。前号の「時うどん」もチョロマカシてましたね。現在のように水道が整備される前は、人々は井戸を使用するほか、水屋から水を買っていたんですね。噺に出てくる「一荷」の壺に入る水は、水屋が天秤棒で担げる2桶分で、色々調べてみると60リットルくらいだそうです。さらに調べて見ると、江戸時代には料金が4文だったそうで、蕎麦の値段16文と比べると、またその重さと比べてみても、ほんとに利の薄い商売だったようです(その辺のところを描いた「水屋の富」という噺もあります)。

笑点の司会でお馴染みの春風亭昇太は、春風亭柳昇の弟子であるだけに新作落語が得意で、古典は下手だと自らネタにしているくらいです。キャラが明るく(軽い?)若手に見えますが、NHKの「ガッテン!」司会の立川志の輔と同期、実は何ヶ月か先輩なのだそうです(落語芸術協会 現会長です!)。
壺算は、お馴染みの噺なので、あまり工夫の余地がないのか、他の噺家は、品物へのトンチンカンなケチの付け方とか、瀬戸物屋の店主のパニクる様子を強調することで笑いを取ります。昇太の壺算の新しい工夫は、弟分の方が今までの型ではなかった最終兵器として登場し、威力を見せつけるところです(ぜひとも動画でみたいものです)。店主がなぜ2度もマケてしまうのかの理由が一番説得力がるように思います。
他に、立川談笑の舞台を現代に置き換えた「薄型テレビ算」があります。これもお薦めです。
985号 2020年4月26日
(4)池田の猪買い
落語に関心をお持ちでない方にとっては、落語といえば笑点、上方の噺家といえば三枝(現6代目桂文枝)や鶴瓶、仁鶴しかご存知ない、というのが実情ではないかと思っております。私も何年か前までは上方落語はほとんど聴いていなかったのですが、ここ3年くらいハマっていて、滑稽噺なら上方の方が断然面白いと思うようになりました。また東京の落語の演目のかなりの数が上方から移植されたものであることも知りました。上方噺家の口演は、You Tube以外では仲々聴けないので、東京に来るお気に入りの噺家の落語会には、なるべく行くようにしています。2006年に開設された大阪の定席「天満天神繁昌亭」には、ぜひとも行ってみたいものです。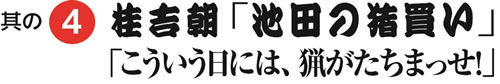
桂吉朝は、2015年に亡くなった人間国宝3代目桂米朝の弟子で、2005年にがんのため50才の若さで、惜しくも亡くなってしまいました。その頃は落語に関心がなかったとはいえ、吉朝のナマの高座に接する機会が無かったことは返す返すも残念です。
さて、「池田の猪(しし)買い」。「薬食いには、獲れ獲れの新しい猪の身でのうてはあかん」ということで、丼池筋からはるばる池田まで、猪肉を求め名人の山猟師を訪ねてあれやこれやという噺です。兄弟子の枝雀のものが面白さなら上かもしれませんが、上方の落語についてまくらで語っているのでこちらを選びました。1991年の上野・鈴本での36才時の高座です。
ご参考までに、談志の口演と聴き比べて見ると、東京への移植のされ方(東京ではもう演ずる噺家はいないようです)や、東西の違いがよくわかります。(お手数ですが「談志 猪買い」で検索して頂くと、すぐに探せます。)好きな噺家なので、また取り上げる機会があるかと思います。
987号 2020年5月31日
(5)青菜
今回は「青菜」。お屋敷の旦那とその奥方との隠し言葉のやり取りに、すっかり感心した主人公の植木屋がウチでもやってみよう!とトライする噺(付け焼き刃モノ)。お屋敷と長屋のギャップ、植木屋とその友達のやり取りをメリハリをつけて演じ分けられるか、どれだけくすぐりをまぶせるか、テンポ良く進められるかで、噺家の技量が測れる演目ではなかろうかと思います。
夏を代表する演目で、気になるのが、暑さの中でキリッと冷えた「柳蔭」。味醂を焼酎で割ったもので、材料だけ見れば大したことはなさそうですが、冷たいのが命。冷やすための深い井戸が持てなかった庶民には高級感のあるちょっと贅沢な酒だったようです。ネットを調べてみるとあったあった。「元祖・日本の夏カクテル『柳蔭』を再現!」(前・後編)でぜひ検索してみてください。「おおっ!くまモンの白岳だ、味醂1に白岳2なのか、ロックが美味そうだな…。」この方の熱意に、私もぜひ一度試してみたくなりました(未成年の方は、お酒はハタチになってからだよ)。
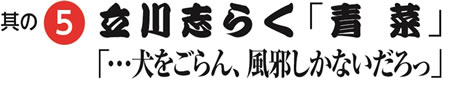
立川志らくは、談志の弟子で、売れっ子四人(志らくと志の輔、談春、談笑)の内のひとり。フランスの元大統領ジャック・シラクに因んで師匠の談志が命名。多才なひとで落語以外にも芝居や、現在はMC・コメンテーターとして活躍中ですね。
テレビに出ていなかった頃は一門会とかよく聴きに行っていましたが、今は「ちょっとなぁ…」で、「グッとラック!」は観ていません。昔のとんがっていたというか「若さの無謀」(30才くらい)で怖いもの無しに飛ばしていた頃のものを。(今回「ニコニコ動画」です。なじみのない方は一度登録が必要です。普通画質のものは無料)
元々は上方の噺だったので、桂枝雀のものも「勢いvs巧さ」の比較としてお薦めです(「鯉も洗いにするとしゃもじですくうか」)。
989号 2020年6月28日
(6)鯉盗人
盗人噺というジャンルがあります。「…仁王かー(匂うかー)」とか「…二衛門半…」などの、使い古されたお約束のまくらに続いて出てくるくらいですから、極悪非道な盗人というのは出てきません。大抵間抜けに描かれ、逆に巻き上げられたり、「こいつはいいやつじゃん!」というのすら出てきます。「だくだく」「鈴ヶ森」「血脈」「夏泥」「出来心」「阿弥陀池」など噺の完成度も高く、演者も楽しげに演っていてわたしの大好きなジャンルです。
上方の七代目 笑福亭松喬(しょきょう、松は伸ばしません)は、「泥棒三喬(松喬襲名前の名)」の異名を頂戴しているくらい盗人噺を得意にしています。面白いのがいっぱいありますから、後日紹介しますね。
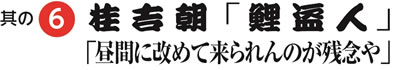
この連載の第4回で、桂吉朝「池田の猪買い」を紹介しましたが、実はそのことで大変後悔しています。ひとつは、この連載は軽目のものから入ろう、親しみやすいご存知の噺から紹介しようと方針を立てていたのですが、ちょっと長めだったなぁと。上方落語はくどいと思われたのではなかろうか心配になったわけです(まぁ、2回目で福笑を紹介した時点で、既にの感はありましたが)。ふたつめには、この噺最初に小拍子の使い方を説明していますが、そこが大変に喧しい。「高音のカチカチが癇に障る」「寝しなに聴こうと思ったのに、眠れないじゃないか」、こういう声が上がっているのではないかと、せっかく「いい噺家でしょう!」と紹介のつもりが贔屓(ひいき)の引き倒しになったんではないか! こりゃ失敗だったと思ったわけです。
そのような反省に立ち、今回は(吉朝が悪いのではなく私が悪いのですが)、汚名挽回のためのとっておき「鯉盗人」です。吉朝だけだと思いますが、他の噺家では演っているのを探せませんでした。まくらを入れて13分弱、本編だけだと7分半の小品ですが、盗人と料理人の、腕や生き方に対する矜恃が聞きどころです(そんな大そうなもんでもないがの)。オチが秀逸。
991号 2020年7月26日
(7)千早ふる
和歌を扱った噺には「道灌」「崇徳院」などありますが、中でもこの「千早ふる」がお薦めです。有原業平の歌の意味を尋ねられ、いい加減な解釈を下し、それに疑問を呈す質問者を力技で納得させるご隠居。知ったかぶりモノの噺です。たくさんの噺家が色んなアレンジを加えていて、個人的にも一番好きな楽しめる噺です。誰が考えたんだろうと調べてみたら、戯作者の山東京伝の「百人一首和歌始衣抄(はついしょう)(1787年)」に「…あまねく人の知るところなれども…」という言葉とともにこの珍解釈が紹介されていて、江戸時代の庶民がこのようなパロディを楽しんでいたのがわかります。
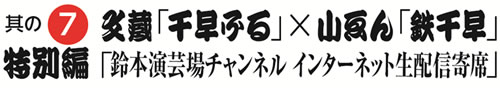
今回は特別編です。コロナ禍で寄席や落語会は長いこと中止・休止に追い込まれています。そんな中、上野の鈴本演芸場が中止になった公演を無観客で興行し、それをネットで配信するという快挙を行いました。7月いっぱいの公開なのでこれを。
寄席では落語ばかりでなく、大神楽・マジック・漫才・紙切…などの演芸が次々と演じられます。3,000円くらいで4時間弱楽しめます。ホールなどで行われる落語会ではNGですが、寄席ではアルコールも含めた飲食がOKです! 寄席は大体空いているし寝てしまっても怒る人は誰もいませんから、気楽に楽しめます。観客あってこその寄席ですが、少しでも寄席の雰囲気をお楽しみいただければ幸いです。
993号 2020年8月30日
(8)おすわどん
挨拶や小噺で会場の雰囲気を整え、スムーズに本編に入るためのいわゆる「つかみ」の話芸がマクラです。用語や当時の習慣について前もって説明したり、落ちへの伏線を張ったり、ちゃんと意味のある要素ですが、世間話や漫談的なのもあります。寄席の持ち時間は大体15分くらいですから、落語会などでその制約がない場合は、いろいろ喋って時間調整が行われます。12、3分の噺で25分持たせるには、10分以上マクラを振らなければなりませんし、元々長い「大ネタ」では、逆にいきなり本編に入ったりする場合もあります。今ではまくらも(が?)面白いという評価の噺家もたくさんいます。柳家小三治がその嚆矢で、マクラだけ集めた本を出しています。小三治の場合は、文字になるとエッセイのように引き込まれて読んでしましいます。
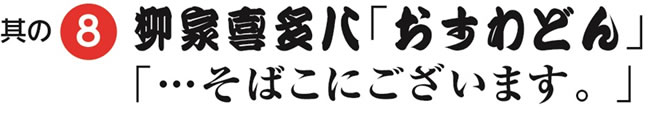
柳家喜多八は、私のベスト3に入る噺家ですが、生の高座に接したことがありません。マイファースト生落語は、2011年2月の「七転八倒の会」で、現3代目蜃気楼龍玉が、金原亭駒七と名乗っていた頃からの、喜多八との二人会(第52回)でした。その時喜多八が入院してしまい、代演は龍玉の兄弟子の桃月庵白酒でした。その後、元気になった後も聴く機会が全くなく、16年に66歳で亡くなっています。18年になって「おすわどん」を初めて聴き、気が付くのが返す返すも遅すぎると、残念でたまりません。
その「おすわどん」、怪談噺の体裁をとった滑稽噺です。短めですが喜多八この時マクラも短めです。初めに言い訳めかしてちょこっと述べていますので、ちょうどいいかなと思いました。落ちもまあまあです。浪人の剣術使い、さも豪傑のような郡山剛蔵(こうりやまたけぞう)という名前で出ています。実は、これ師匠の小三治の本名です。(ネタバレっぽいのですが、客席がなぜ受けているのか、我慢仕切れず書いてしましました!)
995号 2020年9月27日
(9)天使と悪魔
今回は新作落語。落語の本を見てみると、大抵挿絵は、みんなちょんまげを結っています。落語は江戸時代のものみたいな錯覚がありますが、多くの落語が明治以降に作られています(一説には8割がそうとも)。明治時代に作られた「芝浜」「死神」「鰍沢」「阿弥陀池」なども当時は新作だったわけですが、現在では古典落語と位置付けられています。古典落語と新作落語(上方では創作落語)の違いは、大まかにいうと次のようなものかと思います。
1. 戦後につくられたもの(大正時代以降とも)
2. 作者がはっきりしていて、作者以外あまり演じる人がいない
3. 現代が舞台で現代語が使われ(髷物と呼ばれる江戸時代が舞台のものも有り)、その時々のトピックなどが盛り沢山
などでしょうか。
古典至上主義のようなものがまだ根強く、作者の個性が強く現れるため、好き嫌いも多くあるかと思います。三遊亭円丈や桂文枝(元の三枝)、三遊亭白鳥、柳家喬太郎、笑福亭福笑などなど、大勢が活躍しています。
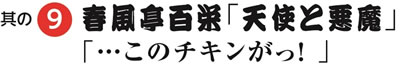
春風亭百恵は新作派の中でも、私の最も評価する噺家です。おかっぱ頭がトレードマークで滑舌が良くない話し方は、古典好きな人には睨まれそうです。今回の「天使と悪魔」は二つ目時代の栄助の時の高座でで、落語マニアの心理とか、新作の置かれている位置、古典との力関係がよくうかがわれる噺です。ほかにも「最後の寿限無」「リアクションの家元」「露出さん」など「大丈夫か!?」と心配になるほどの強力な新作を持っています。「初めての新作」としては「イキナリ来る?」という感じですがご賞味ください。
997号 2020年10月25日
(10)六尺棒
江戸では孝太郎、上方では作次郎という名前が半ば固定している大店の若旦那。中には「明烏」のように堅物もいますが、大抵は親の金・店の金を持ち出しては吉原に繰り出し、度が過ぎて勘当されてしまう道楽息子と相場が決まっています。今回の「六尺棒」の若旦那も親父さんを困らせています。「・・・10時限り」とか「俥」とか出てきますが、江戸時代の文化年間からある古い噺だそうです。10分足らずの小品ですっごく面白いというでもないのですが、「この噺ならこの噺家」の伝でいうと、これなんですね。

笑点メンバーの落語はあまり聴く気がしないのですが、春風亭昇太と三遊亭小遊三はよく聴きます。小遊三はキレのいい江戸弁で語るので、山梨県の大月出身とわかっていても江戸っ子なんだろうなと思ってしまいます
この小遊三の「六尺棒」、まくらがいいんですね。立川談志の一周忌追悼落語会での一席かと思われますが、談志に稽古してもらった縁を語ってます。落語界や寄席の楽屋の雰囲気、何より談志の人柄のいい面がよく窺えて、たのしいまくらです(題字下の一言も、今回はまくらから引用」。談志の口真似もうまく、稽古付けてもらっただけあって、ちらほら談志っぽいところを聴くことができます。
落語芸術協会の、便所でおしりを副会長から昇太の会長就任に伴って現在は参事。「箱根駅伝」という全編まくらの噺もなかなか面白いですよ。
999号 2020年11月22日
(11)関取千両幟
正代関の、優勝と大関への昇進、おめでとうございます。それに因んで今回は相撲噺からと思ったのですが、何にするかほんとに困りました。噺自体は「佐野山*」「大安売り」「小田原相撲」…とたくさんあります。そうそう竜田川*の「千早ふる」も忘れてはいけませんね。ですが、いまとは時代が違うので、八百長(噺の世界では「人情相撲」と言う)的なものが多いのです。その辺に関係なく笑いの取れる「花筏」にしようか、出世物語の「阿武松*」にしようか、悩んだ挙句三遊亭圓生の「関取千両幟」(「稲川*」とも)にしました。
(*印は、現在も年寄名跡に残る四股名)

圓生は志ん生・文楽・彦六と並ぶ昭和の大看板・大名人です。芸について厳しい古典落語至上主義者で、それは全てスタジオ録音の「圓生百席」の刊行に如何なく発揮されています。私などは落語は、観客の拍手や笑声に演者も乗せられることによって、良い高座になると思っているので、疑問に思わなくはないのですが、きちっとした芸がそれによって残っているのは凄いことだと思います。
この噺19分くらいですが、ネタの部分は終わりの7分くらいで、あとは今昔の関取に関する圓生の、相撲通ならではのまくらが楽しめます。(3万貰ってて贔屓がいない? 大錦なの、稲川なの?など、よく整理されてない気もしますが)関取の誠実さと河岸の衆の心意気が気持ちいい良い噺です。
正代関にはこれからも、贔屓(ファン)を楽しませる良い相撲で、長く活躍していただきたいと願っております。
1002号 2021年1月24日
(12)質屋蔵
前の圓生の回で、観客と演者の関係について少し触れましたが、それを感じていただける噺を今回は。
スピーディに強弱・起伏もたっぷりな話し振りに、合いの手よろしく入る笑い声、それに乗せられて、ますますなめらかにトントントン…という典型です。ホール落語だと思いますが、観客と演者の気がピッタリ合って、両者大満足・大成功の一席だと思います。
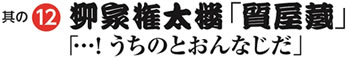
柳家権太楼は、人間国宝 故柳家小さんの弟子で、訛ってるようにも聞こえますが、チャキチャキの江戸っ子です。
この噺、元々は上方のもので、ご当地での読みは「ひちやぐら」となります。この噺は演者もたくさんいますが、権太楼のこの一席が、上に述べた理由で一番だと思います。
おみつさんの哀しい「繻子の帯」(質屋の旦那もなかなかのストーリーテラーです)、定吉の「鬱憤」、熊さんの「悪行と露呈」、それぞれ面白要素がツボにはまってポンポンポンと繰り出され、モタモタした感じがありません。聴き比べてみると、他の演者との差はここにあると思います。おもしろ要素が全部入っていて、繋がっていて、他の演者はその取捨に失敗しているかのようです。
天神様 菅原道真が最後に出てきますが、質入れした「しへい」さんというのは、菅公を太宰府に讒言で左遷したと言われる藤原時平のことです。ここわかりにくかったりするのか、最近は「藤原」と置き換えてあるようです。
1004号 2021年2月28日
(13)桂枝雀「代書屋」「セーネンガッピ、を!」
「こんな人はいないっ!」という人ばっかり出てくる噺の世界でも、ここに登場いたしましたる松本留五郎氏、文句無しに最右翼です。いい大人で生年月日を知らない人っていないすよね。よく大人になれたもんだな。しかし松本氏(他の演者は別の名前で演っています)、枝雀ファン・上方落語ファンの中でスーパースターの地位を確立しています。(元々はこの後に2つのエピソードがある長い噺ですが、現在は松本氏の部分で切る演じ方がほとんどです。)
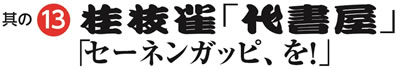
2代目桂枝雀は、人間国宝 故桂米朝の弟子で、残念なことに99年に59歳で没していますが、生前は昭和の爆笑王の名を欲しいままにしました。研究熱心・サービス精神旺盛で、現在YouTubeで聴いてみても、同じ噺であっても同じに演じているものは一つもありません(ほぼ)。この「代書屋」でも、松本氏の本職は「ポン」となっていますが、他では「ガタロ」になっていたりします。
私などは、「ちょっと盛りすぎじゃないの?」とか、そのオーバーアクション、ラ行の巻き舌など、聴いてて疲れると感じる時があります。が、噺家を語る際には絶対外せないビッグネームであり、多数の噺家がこの噺を演じている中、爆発力において他者の追随を許さない、「代書屋といえば枝雀」という一席です。
1006号 2021年3月28日
(14)月に叢雲
古典落語と新作落語があると前に触れましたが、新作の中には作者付き落語(?)というものもあります。噺家自身が作って演じるとそのまま新作となりますが、今回の場合は、落語作家が作って噺家が演じるという形です。昭和の頃からあったようですが、落語作家とと言えば、桂枝雀に「幽霊の辻」を郵送して認められ、その後多くの噺を提供している小佐田貞夫氏が第一人者です。ほかにも、余技的になりますが、中嶋らも氏もいましたね。
にも広がっていけば、古典落語の一つとして定着する佳作だと思います。

笑福亭三喬は2017年に師匠の名跡を襲名し7代目松喬となりました(今回音源は三喬時代のもの)。盗人噺を多く演じていたので、「泥棒三喬」の異名をとっていましたが、その他の古典落語も得意にしています。「月に叢雲(花に風)」は「佳いことには何かと悪いことが起こりがち」という意味で、その風流な響きが昔の時代劇に出てきそうで、盗人ものにはピッタリだと思います。小佐田貞夫氏作で、そのまま古典落語で通る風体をしています。今のところ三喬以外の演じ手を知りませんが、他の噺家にも広がっていけば、古典落語の一つとして定着する佳作だと思います。
1008号 2021年4月25日
(15)松曳き(まつひき)
噺家の高座名は、流派・系統を表す名字に当たる亭号と、一人一人の名前からなります。弟子入り時に師匠に前座名をつけてもらい、昇進の際に改名を行うのが一般的です。亭号はそのままに師匠の一字を貰った名前になりますから、どこの一門かが大抵わかるようになっています。そんな中で一風変わっているのが五街道雲助の一門です。雲助自身、金原亭馬生の弟子で二つ目昇進時に五街道雲助を名乗りました。弟子は、桃月庵白酒(3代目 五街道喜助から)、隅田川馬石(同佐助から)、蜃気楼龍玉(同弥助から)の3人です。これでは誰の弟子かわかりませんが、3人とも実力派なのでそんな心配はないようです(系統としては三遊派・古今亭)。

今回の白酒は、丸ぽちゃの外見に似合わず、毒舌まくらが人気です。「松曳き」は昔からある侍階級を笑い飛ばした噺で「粗忽モノ」ですが、白酒はつまらないところはカットし、さらに粗忽さ(エキセントリックさ)を強調し、得意のクスグリ満載(聞き間違いネタが得意なようです)で、以前のものとは桁違いな爆笑ものに仕立てています。小さん・談志のものと聞き比べても両名人がかすんでしまう出来です。
1010号 2021年5月30日
(16)天王寺詣り
「十二子孝」で親孝行の尊さに触れ、「鹿政談」であるべき正義の形を考え、「千早ふる」で古今の和歌に親しむ、など識字率が低くテレビもラジオもなかった時代に、寄席・落語は、娯楽ばかりでなく教養と常識を学ぶ機能があったようです(かなり強引!)。この「天王寺詣り」も、遠くて行けない人やどんなところか知らない人に「こんなところですよ」とガイドする「地球の歩き方」的な性格を持った噺で、四天王寺の境内とお彼岸の賑わいを活写しています。(大阪の人は「四」を省略して天王寺ということが多いようです)
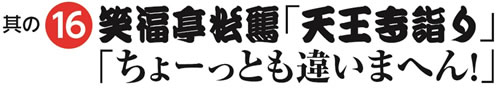
この噺は笑福亭一門のお家芸で、6代目松喬にするか雀三郎(桂ですが)にするか悩んだ末、出だしの「なんや嬉しそうにニコニコと笑うているが…」という語り口が、この人の優しさが現れているようで、6代目笑福亭松鶴(しょかく)のにしました。「らくだ」で紹介しようと思っていたのですが、まぁそれはそれで行うとして…。私もいつか大阪に行く時は、この噺をガイドブックにしてぜひ天王寺詣りをしてみたいと思っています。
※ 無礙性:仏教用語 ここでは「乱暴に」
程度の意味。
1012号 2021年6月27日
(17)やかん
さて、立川談志である(難しい!)。Wikipediaには「その荒唐無稽・破天荒ぶりから好き嫌いが大きく分かれる落語家の一人」とあるように、神と崇める人もあれば、私のように敬遠している人もいます。立川流の創設はともかく落語協会の分裂騒動など、挙措の不明瞭なところもあるかと思います。若い頃の高座を聞くと、硬いといってもいいくらいカチッとした語り口なのですが、後には「…談志の意見や解説、哲学が入り…「客は『噺』ではなく、『談志』を聴きにくる…」と言われるほどになり、落語界ばかりでなく芸能界やいわゆる「文化人」の間でも強い影響力を持つようになりました。私などは「噺をちゃんとやれ!」と思い抵抗を感じてしまいますが。

さて、立川談志の噺である。「根問い(根掘り葉掘りきくこと)」モノの一つ「やかん」を。屁理屈で無理やり言いくるめる・ケムに巻く、これはまさしく談志そのものではありませんか。皮肉でも悪意でもなく、そこを芸にしてケロっとしているところは大したもんだなと思います。他の演者のものと比べても格段に面白く、談志を代表する噺として取り上げて良いのではないでしょうか。
1014号 2021年7月25日
(18)千早ふる
この連載は動画にアクセスして噺を聞いていただくのが前提になっています。(文章だけでは、あらすじには触れないので、何が何だかわからない、ということになってらっしゃるかと)。そのネットにアップされている噺、事情があるのでしょうが、削除されてしまうことがあり、予定していて変更を迫られることがままあります。今回は復活した例。早くしないとまた削除されるかも、ということで、笑福亭福笑の「千早ふる」演者も演題もとり上げるのは2回目になります。
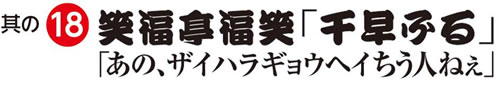
以前にも触れました通り、この噺は山東京伝の百人一首のパロディに原型があります。現在多くの噺家が野心的な演出で競い合っている状況で、どう演ずるのか楽しみな噺です。本寸法で演じていては、つまらないと評価されそうな感じです。そういう視点から観た私の評価では、露の新治・瀧川鯉昇、そしてこの福笑がベスト3です(残念ながら新治と、鯉昇のベストバージョンは未だアップされていません)。噺は、カミシモと言って左右を交互に向いて、会話の人物を演じ分けるというのが基本ですが、福笑は本編ではカミシモを取らず正面だけ向いて進めます。(まくらの一部ではカミシモとっていますので、違いがわかるかと思います。ま、全然違和感が無いので、こんなことはスルーしていただいて結構です)。私はこの噺を聞いて以来「せや!」にすっかりハマってしまい、多用しております。
1016号 2021年8月22日
(19)芝浜
大ネタと呼ばれる噺の分類があります。長編・大作で、主に人情噺ですが、高度の技量が要求されているものです。「大ネタってどんなものがあるの?」という問いには、だれが答えても必ず、この「芝浜」が入っているはずです。「落語中興の祖」と呼ばれる三遊亭圓朝の「酔っ払い」「財布」「芝浜」の題目を織り込んで語った三題噺が元で(諸説あり)、3代目 桂三木助(1902〜1961)が改作し現在の型にしました。登場人物はたった二人ですが、芸術性・写実性の高い噺として完成させました。当然のことながら三木助の十八番で、古今亭志ん生も三木助存命中は高座にかけなかったと言われています(三木助の追悼興行で封印を解き演じています)。
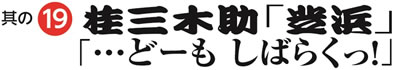
大ネタの筆頭にも挙げられるような噺ですから、噺家のビッグネーム達が、談志を初め大勢演じています。だれのが良い・彼のが好きと、その人によって意見はさまざまですが、まずは、三木助のを聴いてからでないと話は始まらないと思います。今回、お聴きいただけるYouTubeの音源は唯一残っているもので、NHKのラジオ番組用(1954年)の録音で短縮版なのだそうです。人によると、録音用でない高座のものはこの数段上であったと言われています。
…まぁ、しょうがない。
1018号 2021年9月26日
(20)ガマの油
前回の三木助に続いて、今回も古き良き名人芸を。10代目 金原亭馬生の「ガマの油」です。馬生はご案内の通り5代目古今亭志ん生の長子で、弟が3代目志ん朝です。志ん朝についてはまた改めるとして、私は馬生の方が好きですねん!
声・語り口が柔らかで、聴く者に緊張を強いない・リラックスさせる心地よさがあり、噺家にとって得してる声だと思います(瀧川鯉昇の声もそんな感じだと思いますが、独断です)。大勢の弟子の中に6代目五街道雲助がいますが、亭号がバラバラなのは馬生一門の伝統なのかもしれません。
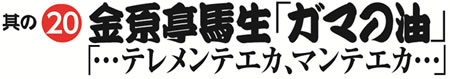
香具師の口上だけで成り立っている噺で、素面の時はそれなりに説得力があった口上が、酒を飲んだせいで呂律が回らなくなり内容までもおかしくなってきます。軽い噺ですが、素面の時の滑らかなたたみかけと、酔っ払った時のそのギャップが楽しめる噺です。「大工調べ」にも通じる「啖呵噺・口上噺」と分類してもいいかと思います。動画でお聞きいただけるものは、26分となっていますが1回終わった後で繰り返しになっているので、実質14分弱です。(題字のおまじないみたいな言葉は、テレピン油とバター(またはラード?)のことだそうです!)
1020号 2021年10月24日
(21)十徳
大阪生まれの噺が東京が舞台になったり、逆に東京の噺が大阪弁で演じられたりすることもたくさんあります。しかし「池田の猪買い」や「天王寺詣り」などのように、地域性が強く置き換えがきかないものもあります。今回の「十徳」も、「大江戸検定」というのがあれば、出題されそうなネタで、東京オンリーな噺です。全編トリビアとシャレで出来ていてます。この十徳、調べてみると羽織との違いは、・腰から下にマチ・ヒダがある ・襟は折り返さず紐は共紐 ・袖に八つ口はなく紋はいれない ・絽か紗で男性が着用…などで、当時の人にとって見慣れない着物には当たらないはずと思いますが、そうでないと噺にならないからね。

三遊亭好楽。ご存知笑点の「ピンクの小粒コーラク!」。彦六の正蔵に弟子入りし、その死後5代目三遊亭圓楽の門下に移りました。本人は東京都豊島区出身ですが、ご両親は大津町引水の出身です。また、惣領弟子の好太郎も引水の出で、なかなか熊本との縁が深い。笑点では「よせよ!」とか「仕事がない」「お金がない」と、自虐ネタが売り物のちょっと情けないキャラクターですが、実際はそんなことはない実力派です。 ま、笑点だからしょうがないか。
(ところで、権助はどこ行った?)
1022号 2021年11月28日
(22)にらみ返し
本名 郡山剛蔵(こおりやま たけぞう)。東京出身、教員の息子。バイクのツーリング、オーディオ、俳句など多趣味。2009年に重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。この10月10日に亡くなった10代目 柳家小三治です。(合掌)同じく人間国宝であった5代目小さんの四番弟子で、「小三治」は、5代目を初め、何人かの小さんがその前に名乗っていた柳家の出世名です(小さんは、柳家の最高名跡=止め名)。「まくらの小三治」と呼ばれるくらい「まくら」が面白い噺家として知られ、「まくら」だけを集めた本も何冊か出版されています。私も文庫本で2冊持っていたはずですが、すぐには出てきませんでした。とても面白く、こうなるともうそのまま良質のエッセイです。弟子の柳家喜多八によると、昔はまくらなしですっと噺に入っていたそうですが。
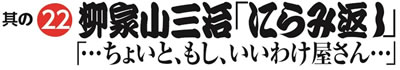
柳家ですから滑稽話が得意で、どの噺をあげてもさすがの出来ですが、今回は「にらみ返し」を。噺の良し悪しは話術の巧拙で決まりますが、仕草・振りも重要な要素になります。そんなところから落語自体が「仕方話」と呼ばれますが、仕草・振りが決定的な要素になるものをジャンルとしての「仕方噺」とも呼ばれます。「蒟蒻問答」がすぐ浮かびますが、「にらみ返し」も演者の表情が見えると面白さが倍増します。小三治は顔もいいですからね。
1024号 2021年12月26日
(23)井戸の茶碗
初めて聴いた時の出来不出来で、噺と噺家の評価が決まることがあります。今回の三遊亭遊馬「井戸の茶碗」がそれに当たります。もちろん良い方の意味で。5代目志ん生のが名演と言われていますが、ちょっとこなれすぎた感じです。武家噺なので遊馬のが、ちょうど良い「折り目」があるように思います。
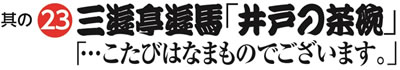
「和樂(2014年10月号)」によると、国宝指定の茶碗は全部で8つ。その中に「大井戸茶碗 銘 喜左衛門」というのがあります。元々は朝鮮半島で焼かれた日常使いの雑器で、豪華絢爛というのではなく、「粗く素朴な味わいが「わび茶」を大成した利休らの目にとまり…(略)」というところがポイントで、日本人の美意識も大したものです。なぜ「井戸」というかは、「見込み(茶碗の底に至る内側の部分)」が井戸のように深いところからついたという説もあるそうですが、不明というのが定説とのこと。
三遊亭遊馬は、笑点の水色・小遊三の弟子です。酒については嗜むというより、たしなめられることの方が多いという噂があります(笑)。最初に聴いた印象が良かったので、贔屓にしたいと思っていますが、残念ながら生では聴いたことがありません。この噺、登場人物のみんなが実直で善人という明るい噺で、客・演者の両方から人気のあるいい噺です。
1026号 2022年1月30日
(24)グリコ少年
三遊亭圓丈。新作ばかりが取り上げられますが、昭和の大看板6代目圓生の弟子ですから古典の実力も一級品です。「圓生名跡争奪対決」で鵬楽と競った時に、ネットで「百年目」を観ましたが、実に素晴らしい出来でした。

一応、古典もスゴイですよと断った上で、今回のご紹介は新作「グリコ少年」です。2018年7月の高座ですが、最初の方は何言っているかわからないし、カンペは見てるし、弟子もつくし、ちょっと痛々しい感じがあります。それはともかく、この噺は、わたしの基準で言っても落語と呼ぶのはちょっときついです。どちらかと言えばアメリカのスタンダップコメディのスタイルに近いと思います。
1944年の生まれだそうで、私と11歳違いです。ですから10年遅れで、噺の内容が私ともかぶってきます。私も貧しい時代だったのを知っているので、うまい棒の話・バナナ・ワタナベのジュースの素…、圓丈の人生と共にある「駄菓子愛」が胸を打ちます(涙)。
古典を演る時は眼鏡を外していました。2021年11月30日、76歳で永眠。合掌。
1028号 2022年2月27日
(25)宿屋仇
今回は「宿屋仇」。(東京では「宿屋の仇討」)宿屋への到着から、色々大騒ぎがあって結末に至る、それまでの流れが崩せないきっちりした噺です。落語には「本寸法」と言う言葉があって、「本来の話を崩していない・正統派である」という意味で使われていますが、この話は、その流れを崩せないので、噺家の個性とか自由な演出がしづらい難しい噺と言えるのではないかと思います。

桂吉朝のこの高座は、本寸法の演じ方では最高だと思います。登場人物が多彩で会話が多い、いわゆる「ほうばるネタ」と言うらしいですが、この辺は吉朝の独壇場です。これに対して、桃月庵白酒の演じ方は、ちょっと崩した形です。(ぎりぎりセーフ!)相撲の場面では輪島や双羽黒が登場しますし、聞いた話だという言い訳は「高座で噺家が演っていた」となっています。こちらも私は大好きです。この噺についてはこの二人が双璧だと思います。
桂枝雀の高座では、旅日記をつけていた侍が聞こえてくる三味線の音に、思わず知らずに体がリズムを取り始める演出があります。同じ一門ですから吉朝もそうやってるかな?と思いながら聴くと楽しくなります。
1030号 2022年3月27日
(26)近江八景
「近江八景」は上方発祥の噺。「八景」の知識が乏しくなった現在では、途中も落ちも、なかなか伝わらないのであまり演じられていません。三喬(現7代目 笑福亭松喬)も、マクラでその説明に時間を割いています(ちょっと早口なのが残念)。

中国の「瀟湘八景」に倣って優れた風景を選定したもので、地名と事象をセットにしています。近江八景は「粟津晴嵐、堅田落雁、石山秋月、比良暮雪、矢橋帰帆、三井晩鐘、唐崎夜雨、瀬田夕照」(地名の後に「の」を補って読むようです)。膳所城も名勝だったようですが、瀟湘八景の様式に合わせているので含まれていません。この八景、東アジアや日本国内に多数選定されているようです。熊本には無いのかと調べてみたらありました!熊本市の水源地「八景水谷(はけのみや)」です。こちらは「三嶽青嵐、金峰白雪、熊城暮靄、壺田落雁、浮島夜雨、龍山秋月、亀井晩鐘、深林紅葉」と瀟湘の様式から少し外しているようです。狭い地域のことでもあり、帰熊の際にはぜひ訪れてみたいと思います。そして「落雁」、空から舞い降りる雁の群れのことだそうですが、お菓子にもありますね。Wikipediaで調べたら、変種の中に「熊本県大津町の伝統菓子」として「銅銭糖」が掲載されていました。ちょっと、嬉しい。
1032号 2022年4月24日
(27)人形買い
他の噺・噺家もしばらく続きますが、現在のところは笑福亭仁鶴の「人形買い」を聴きながら、夜寝ついています。なので、最後まで聞いたことがほとんどなく改めて何度か聴き直し、こんな下げだったかと気づいた次第です。仁鶴は、70年代に喉を痛めてトーンを抑えたじっくり聴かせる芸風に変わったそうで、睡眠誘導効果の高いなんともユルイ、子守唄のような心地よい話し方です。

江戸時代のお金の話なので少し解説を。24軒から96文ずつ集めて2貫400になる、というところが出てきます(1貫は1,000文で、1/4両=4朱=1分)。96×24だと2,304文にしかならないのでは、と思いますが、なんと江戸時代には96文を紐に通すことで、100文として通用する商慣習だったそうなのです(九六銭 クロクゼニ)。それで2貫400と言っているのですね。これは明治になってから廃止されたそうです。銀行ではたった1円でも合わななければ、何度も計算し直す、という話を聞いていたのでびっくりですね。
仁鶴、NHKの土曜日お昼の番組の司会者を長らく務めていましたが、奥様が亡くなってから5年ばかり出演していませんでした。どうしたのかなと心配していましたが、骨髄の病気で2021年8月17日、84歳で永眠しました。合掌。
1034号 2022年5月29日
(28)天神山
「異類婚姻譚」の一つ「天神山」は上方演目の噺です。移植された東京では「安兵衛狐」となりますが、ストーリーがだいぶ違っていて「天神山」の方が断然面白いです。今回の動画は昭和54年とありますから、枝雀が40歳になる前のグイグイ上り調子の頃のもので、後のものに見られるような、気になる巻き舌もオーバーアクションもまだありません。

私が一番好きなのは、胴乱の保兵衛と狐獲りの角右衛門のやりとりのところ。何と心優しい男たちではありませんか! ここがいいところなのに東京のものは、カンタンに済ましているのでそれだけで魅力半減です。ヘンチキの源兵衛も天邪鬼が度を越しているだけで実害はなさそうですし。終盤も元ネタとなった人形浄瑠璃に寄せたスッキリしたサゲで、なかなかよろしいかと(浄瑠璃・歌舞伎を元にした噺は歴史がある分、上方の方が一枚上と思うのは贔屓目でしょうか)。弟子の桂雀々のものも、なかなか良い出来ですが、無料のネットには上がっていません。権利とかいろいろあるのでしょうが残念です。
噺とは全然関係ありませんが、狐が獲られる舞台の安井の天神様は、その昔真田幸村が戦死した地だそうです。
1036号 2022年6月26日
(29)鶴満寺
今回は有料チャンネルの「無料お試し」がお薦め。こちらの方が絶対面白い! こういう言い方はアレですが、気に入ったら続ければいいし、いやだったら期限内に解約すれば良い(忘れずに!)。無理には言いませんが。「桂雀々 鶴満寺」で検索してみてください。

噺のお楽しみは、その「話術」にかかっていますから、ラジオなど音声だけでも満喫することができます。それに「表情・身振り」が加わるとさらに面白くなります。今回末尾掲載のQRコードからは、無料配信の雀々の鶴満寺が楽しめますが、これが無観客なのです。落語のもう一つの重要な要素「観客」が抜けているのですね。これだけ聴くと十分面白いのですが、雀々の芸は観客と一体になってお互いに盛り上がって行くスタイルなので、反応がないとちょっと……(本人もやりにくいでしょうね、稽古と同じだもん)。芝居もコンサートも、いい観客があればこそ!で、私は「空間芸術」と勝手に呼んでいますが、やっぱり会場での生が一番ですね。有料の方は長めのまくらで十分暖めた上での本編なので、もー面白いっ! 師匠は枝雀。この噺と「天神山」は、ぜひ会場で聴きたい噺家です。
1038号 2022年7月24日
(30)夏泥
私の初ナマ落語は2011年の2月5日(土)、今回の三代目 蜃気楼流玉の落語会でした。演目は「臆病源兵衛」と「鰍沢」で、この鰍沢が絶品で、上手い噺家だと感心したものです(初ナマのくせに厚かましい!)。

龍玉は、五街道雲助の三番弟子で兄弟子に桃月庵白酒、隅田川馬石がいます。雲助版の同じ噺を聴いてみると、なるほど口調がよく似ています。全員実力・人気ともにある私の好きな一門です。
この噺は別名「置き泥」ともいい、上方では「打飼盗人」といいます。被害者(?)の男の金欠ぶりに同情して、逆に泥棒の方がお金を恵んでしまうという噺ですが、最近は被害者がカサにかかってお金をむしりとる方に力点が置かれているようで、これでは泥棒が単なる間抜けで被害者が上手くやったということになり、あまりいい感じはしません。龍玉のは、次々に出てくる要求に対する一つひとつの愚痴のセリフに、力量があるからこそですが泥棒の人柄の良さが、じんわり滲み出て、なんかいい気持ちになります。
1040号 2022年8月28日
(31)狼講釈
「狼講釈」は、「五目講釈(東京にはこの名前の噺が有り)モノ」の一つで、よく知られている講釈のサワリの部分を支離滅裂に並べて煙に巻く噺です。覚えるのも大変でしょうが、まず息が続かないと。
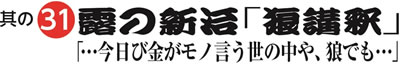
露の新治は、存命の落語家の中で私が一二に挙げる噺家です。大阪が拠点なので東京では中々聴けません。2回チケットを取ったことがあるのですが、コロナ禍のために2度とも中止になり、残念な思いをしています。大阪に行けば済む話なのですが、お金をかけて行くのならいい演題に当たりたいと、チェッしてるだけで、ナマ新治は未経験です。ネットにも少なく、「千早ふる」「中村仲蔵」「動乱の幸助」…など紹介したいのですが、上がってないので今回は「狼講釈」を。「なんだ間に合わせか」と思ってはいけません。これも削除される可能性が高いので、ぜひお聴き逃しなく。 ※森元総理のくだりは「フーアーユー捏造報道」で検索すると真実がわかります。謝罪しなければならない人がいるみたいですね。
1042号 2022年9月25日
(32)ハンドタオル
立川志の輔は談志の弟子で、龍角散のCMの人、ためしてガッテン(→ガッテン!、既に番組終了)の人です。新作も古典も演りますが、私の中では新作の人です。立川流の中でも、安心して身を任せられる絶対面白い噺家です。

新作の「ハンドタオル」。この噺はマクラからして大爆笑。そのまま登場人物の会話だけでトントントントンと進んでいきます。地(セリフ以外の状況を説明する部分)は一切ありません。会話が進むにつれ切れ目のないマシンガンギャグが続きます。私もよくわかりませんが「意味論」的な、知的な面白さがあるような気がします(?)。今回のものには、落語の豆知識もついています。せっかくですからスキップせずにこちらもどうぞ。
志の輔の噺で一つ難をあげるとすれば、声質がちょっと聞取り難いかなぁという点です。その上面白いので、気を入れて聴かなければなりません。就眠ルーティン向けには、あんまりよくないなと感じております(個人の感想です)。
1044号 2022年10月23日
(33)壷算
この噺を聴いて「仁鶴は名人だったんだ!」と認識した一席です。「壺算」は、この連載の始めの方で、春風亭昇太のものをとりあげました。あれはあれで良いと思うのですが、この一席は上方噺の、より原型に近いものだろうと思います。
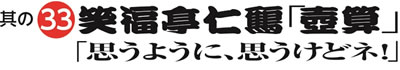
男がアニキ分のところを訪ねて、水壺が必要になった理由を述べるくだりが長いです。この辺は、現在では省略されて演じられていますが、省略された理由は、時間の制約の他に、面白く演じる力量が多くの噺家に伴わなかったからだと思います。仁鶴の語り口が、男のとぼけたボケに心地よく調和し、うまいなぁと感心させられます。寝がけに聴くと、たいていこの間に寝入ってしまします(私はこの1ヶ月くらいはこれで寝落ちしています)。後半は他と大きな違いはありませんが、最後まで安心して聴くことができます。桂米朝に稽古をつけてもらったようですが、桂枝雀も教えを受けたそうなので、この3人の聴き比べをしなくては!と思っているところです。
1046号 2022年11月27日
(34)明日に向かって開け
三遊亭白鳥は圓丈の弟子で、入門時の名は「新潟」(出身がすぐわかりますね!)でした。落研未経験のほぼ初心者で入門しましたが、今では大勢の新作を演じる噺家の中でも、春風亭百栄と並ぶ第一人者となっております(個人の感想です)。改作はやっても古典はやりません(やれません?)。こう見えても名人・圓生の流れですから、正式には一門の「三ツ組橘紋」が定紋ですが、独自の「白鳥紋」を使用しています。出囃子はもちろん!「白鳥の湖」です。アディダスを意識したの3本ラインを入れた着物を着る時もあります。
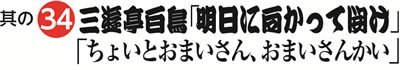
マクラの部分で「新作落語で古典落語」「恥ずかしいのに江戸前の仕草(音声のみなのでよくわかりませんが…。時々ドタンバタンと音がしています)」「くだらないのに人情噺」と、本人が言っていますので、そこらへんが鑑賞のポイントというところでしょうか。私的にはおかみさん(金庫ですが)の、江戸前な気っ風のいい姐さん口調が、なかなかいいなと思っております。
1048号 2022年12月25日
(35)聖夜
クリスマスなので「聖夜」を。演ずるのは枝雀の弟子 桂雀三郎。この雀三郎、前回はどのように紹介していたか調べようとしたら、なんと今回が初めてと分かりびっくり!。とうの昔に取り上げているつもりだったんですが。爆笑派ですが「野太い声による豪快な本格実力派(Wikipedia )」で、新作古典ともに演じます。今後ネット上で見つけたらどんどんとり上げます。笑いたければ雀三郎です。
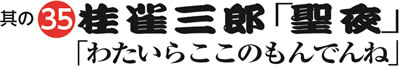
太融寺というお寺での高座ですが、家族連れが大勢いる模様。3年保育とかの身近な言葉に子供達が喰い付きました。他の噺のパロディがちりばめられているし、大人のハナシも出てくるのに、わからないくせにゲラゲラと笑っております(おかげで聴き取りにくいところも)。演者と観客が一つになった大盛り上がりの面白くて楽しい落語会です。小佐田哲也原作によるもので、かなり希少で、これが削除されたらもう聴く機会はないかもしれませんゾ!(広告が多くてすいません、スキップしてくださいね)
1050号 2023年1月29日
(36)更屋敷
マクラについてどう思われますか。マクラが楽しみな噺家も大勢いますが、30分の高座の半分がマクラとなると「早くやれー!」と言いたくもなって来ます。3代目桂春団治はマクラは振らずすぐに噺に入る型で、スッキリしていていい感じです。ちなみに上方の演芸界では名前まで言わなくても「3代目」といえば春団治のことで通用するそうです。(他には「6代目」の笑福亭松鶴だけ。)

すでに全員故人となった上方四天王の一人ですが、春団治は、「淡々さと艶やかさ」「綺麗な芸」と評されています(羽織を落とすし仕草に要注目!)。私はその他に、ちょっとおっちょこちょいっぽい人物を演じる時のセリフや仕草・表情が、可愛らしくてとても良いと感じています。今回はそれがよくわかる「皿屋敷」を。東京では「お菊の皿」と言います。特に若手などが演じる時は、お菊が現代のアイドルになってしまう型が多いようです。それもいいけど、ここでは本寸法の上方の芸をどうぞ。
1052号 2023年2月26日
(37)桃太郎
「真田小僧」「佐々木政談」「雛鍔」など、子供がたくみな弁舌で大人をやり込め、小遣いをせしめるという噺が多くあります。この手の噺は、子供の一休さん的な頓知を楽しめばいいのでしょうが、私は「こまっしゃくれたガキが!」と思え、あまり好きではありません(まぁ目くじら立てるほどでもありませんが)。「桃太郎」もその一つですが、福笑はこの短い前座噺に、子供が親に本格的なバージョンを披露するというパートや小ネタ・くすぐりを加え、本編20分以上の本格噺(?)に仕立てています。

福笑は新作の他に、このように古典に工夫を施した改作を多く手がけ、決して古典をそのまま演じるということはありません。新しい息吹を吹き込んでいるわけです(褒めすぎの感もありますが…)。今回は動画です(最初の方、画像が少し乱れていますが)。福笑独特の正面だけ向いて語るという、「上下(カミシモ)の振り」を廃した、その迫力も見どころです。
1054号 2023年3月26日
(38)試し酒
酒飲みの噺は酒癖の悪いのを笑うものが多く、あんまり好きではありませんが(自分のことは棚に上げて!)、この柳家権太楼(3代目)の「試し酒」は聴いて気持ちの良いものの一つです。
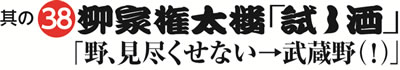
主人公の久蔵は、ガサツな山家育ちの典型的な下男役の男ですが、性格はいたってよろしい! また、都々逸を披露したり故事の蘊蓄を語るなど、なかなか知的な人物です。「儀狄」なんてこの噺を聴いて初めて知りました!(落語は色々とためになります!) 権太楼の語り口が久蔵の個性にピッタリ合って、単なる爆笑派の看板以上の実力を感じさせます。ただ騒々しく語ったのではこうはいかない。
この連載の第12回「質屋蔵」の中で、権太楼は柳家小さんが師匠と書きましたが、元々は柳家つばめ(5代目)の弟子だったのが、その死去にともなって、大師匠に当たる小さん門下に直った、というのが正確でした。訂正します。
1056号 2023年4月23日
(39)初天神
6代目笑福亭松鶴は、酒を初めとするさまざまな伝説(弟子たちが、マクラでいろんな話を聞かせてくれています)や、風貌・声から豪放な「力」の演じ方をするように思われがちですが、丁寧で緻密な一面もあります。マクラの中で、洋服屋が子供を相手に丁寧な口をきいているところは、感心させられました。
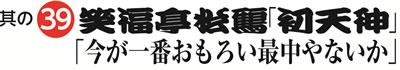
初天神とは、大阪天満宮(近くに定席の、天満天神繁昌亭があります)で、1月25日に開かれるその年最初の縁日のことです。そこが舞台ですから、この噺は上方発祥ということになります。
子供が出てくる噺ですが、「こまっしゃくれた悪ガキ」と描くか、「口達者だけど良い子供」と描くかの、2タイプあるようです。今回のこれは後者ですね。どちらかというと父親に問題がありそうです(?)。エピソードも、「羽織」「果物屋」「飴屋」「凧」に絞っているのも、キリッとした感じを与えてくれているように思います。
1058号 2023年5月28日
(40)火焔太鼓
今回は古今亭志ん生の「火焔太鼓」を。落語ファンのみならず一般においても、現在では常識とか教養として語られる演目となっています(ホント?)。多くの噺家が演じていますが、志ん生のものを超えているものはありません。息子のやはり名人と呼ばれた志ん朝も演っていますが、整理され過ぎているというか、上手すぎてつまらなく感じられます。やはり志ん生の自由闊達な「フラ」(落語の世界で言われる、持って生まれた愛嬌、おかしさ、その雰囲気のこと)あっての演目です。

明治末期にすでにあったものに、昭和の初め志ん生が多量の「クスグリ」(演者オリジナルの小ギャグ)を入れて、ほぼ新作とし仕立て直したものとあります(wikipedia)。ほとんどクスグリで出来ているとも言われますね。
1060号 2023年6月25日
(41)湯屋番
今回は柳家小三治の「湯屋番」を。勘当になった若旦那が、居候先に居づらくなり湯屋に奉公に出たという滑稽話で、柳家のお家芸です。この演目と小三治には逸話があります。あるイベントで、毒蝮三太夫と小三治で落語を演るという企画があり、毒蝮が湯屋番を演ったあと、小三治も湯屋番をぶつけたそうです。毒蝮よりはるかに客を笑わせたそうですが、毒蝮も立川談志から稽古をつけてもらっていたとはいえ、素人相手に大人気ないなという気がしますが…。
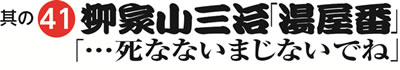
この話には続きがあり、私の筆力とスペースでは伝えきれないので、関心のある方はWikipedia 柳家小三治でぜひご覧ください。プロの意地が出てしまったのでしょうね。そこんとこ読んでみると、それぞプロだよな!と感心してしまいます。アップのものはその時の高座のものではありませんが…。(今回決して手を抜いたわけではないです!)
1062号 2023年7月23日
(42)ちはやふる
「ちはやふる」は何回か取り上げていて、連載タイトルに偽り有りの感もありますが、展開にいろんな工夫ができ噺家の実力を測るに最適の噺で、第18回で紹介した福笑のものと今回のもの、そしてもう一つがベスト3だと評価していてどれも落とせないのでどうぞご了解ください(3つ目は見つけ次第すぐ取り上げます)。瀧川鯉昇は噺に常に手を入れる噺家なので、すでにいろんな型でいくつもネットに上がっていましたが、(実は探していたものとはオチがちょっと違うのですが)この型のものがやっとアップされ、お届けすることができるようになりました。

噺中に出てくる「スカイツリーと名前を変えたな」というくすぐりは、東京スカイツリーの開業時、東武線の駅名が「東京スカイツリー駅」に改称されましたが、その前までは、有原業平の数年に及ぶ東国滞留に因んで付けられた「業平橋駅」という名前だったことを指しています(現在も「旧業平橋」と併記されています)。
今回は動画なので、お分かりいただけると思いますが、お辞儀をした後少し間を開けるという独特の入り方で、お客の視線を掴みます。噺家としても得な顔ですよね。コーエン兄弟の映画によく出演しているスティーブ・ブシェミに、似てると思いませんか? 鯉昇自身、豊川悦司主演の「必死剣 鳥刺し」で好演してましたしね。
1064号 2023年8月27日
(43)禁酒関所
今回は、笑福亭松喬(6代目)の「禁酒関所」を。名人笑福亭松鶴の弟子で、現7代目松喬(元 三喬)の師匠です。10分超のマクラの中で、上方と東京の噺の成り立ちや特徴・違い、東京への演題の移植などについて語っています。なかなか勉強になるマクラです。そういうことで、東京では「禁酒番屋」となります。東京の侍ネタでは、多くはきちっとした侍言葉を使いますが、この噺では酔っ払っているので、当然のことながらへべれけに乱れます。この辺は生まれが上方の噺だからかもしれません。ちょっと3人目のくだりがアレですが、よくできた噺です(笑)。

「水カステイラ」は小僧の苦し紛れの言い訳ですが、なかなか高いワードセンスを発揮していると思います。私もいつかは飲み屋で「水カステイラっ!冷でっ!」と注文をしたい誘惑に駆られていますが、同席の仲間ばかりでなくお店の人も、この故事(?)を知っていないと白けるだけなので、今はひたすら機会を待っているところです。
1066号 2023年9月24日
(44)道灌
立川談志の「道灌」。談志については説明は不要ですね。天才とか「私にとっては神様ですっ!」という落語ファンが多数います。私は正直言って苦手です。若い頃の真打なりたての頃はカチッとした端正な話し方だったのが、なんでこうなったんだろう?と思います。でもこの「道灌」を聴くと、柳家一門の1st稽古の前座噺であるとか、上下(かみしも、話す時に顔の向きを変えて複数の人物を表現する)の取り方をはじめとした稽古の付け方とか、三遊亭金馬の真似とか、落語トリビアが散りばめられていて楽しいし、まぁお得な感じは確かにします。

噺には、短歌をテーマにしたものが色々ありますが、「ちはやふる」(在原業平)、「崇徳院」(そのまんま崇徳上皇)と並んで、「道灌」は三大短歌噺と呼んでいいかと思います。じゃ誰が詠んだの?というと、答えは、後醍醐天皇のお子さんの兼明親王です(中村和馬(?)よりこっちだろう!)。それをちゃんと伝える噺家もいますね。落語ってほーんと教養ですね!